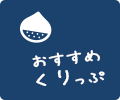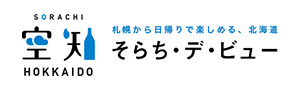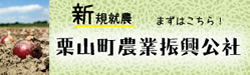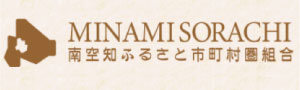本文
令和2年度教育行政執行方針
令和2年第1回栗山町議会定例会の開会に当たり、教育行政執行方針を申し上げます。議員の皆さんをはじめ、町民の皆さんのご理解とご協力をいただきたいと存じます。
国は第3期教育振興基本計画において、「超スマート社会(Society5.0)」の実現に向けた技術革新が進展する中、「人生100年時代」を豊かに生きていくためには、若年期の教育として「知識・技能の習得」や「思考力・判断力・表現力などの育成」、「学びに向かう力・人間性等の涵養」の3つの資質・能力の育成を掲げ、生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高め働くこと、地域社会の課題解決のための活動につなげていくことを今後の教育政策の重点事項として位置付けました。
一方、北海道は北海道教育推進計画において、「自立」と「共生」の二つの基本理念のもと、「ふるさとを想い、グローバルな視野で共に生きる力の育成」と「学校・家庭・地域・行政の連携による、人口減少に対応するための教育環境の形成」の二つを重点事項に位置付けました。
本町では、教育推進の基本理念である「心豊かで、たくましく、力強く未来を切り拓く人づくり」のもと、町民誰もが生きがいのある充実した人生を送ることを願い、教育委員会が行うすべての活動を通して、「ふるさと教育」を推進してまいります。
以下、具体的な方針について、「学校教育」、「社会教育」、「自然体験教育」、「栗山町立北海道介護福祉学校」の4分野に分けて申し上げます。
第1分野 学校教育
新学習指導要領を「学びの地図」として、学校と地域社会が連携・協働しながら「社会に開かれた教育課程」を実現し、子どもたちの「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」のバランスのとれた「生きる力」の育成を図るとともに、学校教育の改善・充実を生み出す「カリキュラム・マネジメント」の確立が重要であります。
また、多様化する教育内容に対応するため、教育環境の充実や教職員が子どもたちと向き合うための時間の確保、さらには、幼児教育から高等教育までを見通した教育が重要であります。
そのため、特に重視することを3点申し上げます。
1.次代を担う子どもたちの資質・能力の育成
子どもたちの学力向上に向け、全国学力・学習状況調査や各種 学力テストなどのさらなる活用と分析を図るとともに、教員の指導力向上のため、栗山町教育振興会や教育研究事業の充実を図り、主体的・対話的で深い学びを実現し、学習の質を一層高める授業改善に取り組んでまいります。
また、小・中の一貫した外国語教育の実施や論理的思考を育む プログラミング教育の導入をはじめ、学校と家庭が連携して家庭学習に取り組むなど、望ましい学習習慣や生活習慣の定着を 図ってまいります。
さらに、地域資源や地域人材など、地域の教育力を最大限に活用した教育活動を継続して実施するとともに、コミュニティ・ スクールや小中高ふるさとキャリア教育の充実を図り、子どもたちが「ふるさと栗山」への愛着や誇りを深め、未来に向かって新たな価値を創造する資質・能力を育む教育の推進に取り組んでまいります。
また、子どもたち一人ひとりの実態に応じた学習を進めるため、特別支援教育支援員を継続して配置するとともに、認定子ども園や保育園と小学校の連携、小学校間の小・小連携や中学校を含めた小・中連携の強化により、横断的で一貫した教育課程の充実を図ります。
学校給食につきましては、安全・安心な学校給食を提供するとともに、関係機関・団体の協力のもと、栗山町産食材のみを使った「ふるさと給食」の拡充を図ってまいります。
2.教育環境の整備
学習環境の充実を図るため、老朽化が進む学校施設や設備の計画的な修繕を実施するとともに、学校ICT環境整備を進めてまいります。
子どもたちの安全確保につきましては、通学路の安全確保に取り組むとともに、災害時における緊急連絡手段の整備を図ってまいります。
また、子どもたちが安心して学習やスポーツ活動に取り組めるよう、各種就学支援により保護者の負担軽減を図るとともに、子ども夢づくり基金による支援を継続してまいります。
さらに、学校における働き方改革「アクション・プラン」や「部活動の方針」に基づく取組を推進するとともに、校務支援システムのさらなる活用を促進し、教職員が子どもたちと向き合う時間を確保してまいります。
3.栗山の高等教育を担う栗山高等学校への支援
本町の産業を担い、まちを支える人材を育成する栗山高等学校が今後も存続していくために、生徒募集間口維持に関する活動や、高校と町が連携しながら生徒確保に関する取組を継続して展開するとともに、生徒に対する各種助成制度などの支援に取り組んで まいります。
また、「北海道栗山高等学校の魅力づくり委員会」において町民の皆さんとの議論を深め、「魅力ある高校・選ばれる高校」となるよう持続可能な地域での高校づくりを進めてまいります。
第2分野 社会教育
すべての町民が幸せを実感できる社会の実現を目指し、「いつでも、どこでも、だれにでも」を合言葉に、町民一人ひとりが、生涯にわたって主体的に学ぶことができる環境をつくることが重要であります。
そのため、特に重視することを4点申し上げます。
1.町民一人ひとりの主体的な学びの機会の提供
幼児期から学童期、青年期、壮年期、熟年期に渡る一貫した学びの機会を提供するため、町民の自主的な学びの場である町民講座を 継続して実施するとともに、子育て世代への家庭教育支援を行うなど、学習機会の充実を図ってまいります。
また、青少年育成会などと連携し、子どもたちの自主的な活動を促すリーダー研修事業を充実してまいります。
文化活動につきましては、文化連盟などと連携し、総合芸術祭開催の継続と、文化振興基金を活用した町民や芸術家の自主的な活動、伝統文化の継承などを支援してまいります。
2.生涯スポーツの振興
町民誰もがスポーツに親しみ、心身ともに健康に過ごすことができるよう、スポーツ推進委員や体育協会などと連携し、各種大会を開催するなど、いつでも気軽にスポーツに取り組むことができる機会の充実を図るとともに、スポーツ団体の活動支援などを通してスポーツの普及・振興を推進してまいります。
また、スポーツ施設につきましては、指定管理者や関係団体と連携を図りながら適切な維持管理を行ってまいります。
3.町立図書館の活用
多様化する町民の学習意欲・読書意欲に対応するため、ニーズを把握した図書の充実を図るとともに、さまざまな資料や情報の収集・整備を行い、知識や情報を得ることができる環境を整えてまいります。
また、乳幼児期のブックスタート事業や就学前児童の保護者への絵本リスト配付事業など、幼児期から家庭での読書習慣を身に付ける家読(うちどく)事業の継続をはじめ、専門司書の継続配置により、学校図書室の充実と子どもたちが本に触れる機会の拡大を図ってまいります。
さらに、図書館を活用した美術・芸術作品展の開催など、町民に親しまれる施設として充実を図ってまいります。
4.国際・地域間交流の推進
子どもたちの豊かな感性や国際感覚を育むため、海外の生活や文化に触れる青少年海外派遣事業「少年ジェット希望の翼」を継続するとともに、イングリッシュキャンプ英語コミュニケーションスキル研修を継続して実施し、福島県川俣町の子どもたちと交流しながら英語によるコミュニケ―ション能力の向上を図ってまいります。
さらに、姉妹都市である宮城県角田市との子ども交歓のつどいや勤労青年研修事業を継続してまいります。
第3分野 自然体験教育
国蝶オオムラサキの発見以来、本町の自然体験教育は、町民有志の30年以上にわたる献身的な自然保護活動に支えられ、多くの町民の皆さんが自然体験を通して、栗山の自然の素晴らしさや栗山の人たちの凄さを知り、栗山で暮らすことに自信と誇りを持ちながら生活しているものと確信しております。
将来にわたって豊かな自然環境を守り、さまざまな自然体験教育を通して子どもたちがふるさとに愛着や誇りを持ち、「ふるさとは栗山です。」と胸を張って言うことができるよう、その学びの環境づくりを推進していくことが重要であります。
そのため、特に重視することを2点申し上げます。
1.豊かな心と郷土愛を育む自然体験教育
雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウスを拠点に、ハサンベツ里山、夕張川など、身近な自然環境をフィールドとして活用し、「ふるさと栗山」の自然や栗山の先人たちの素晴らしさを学ぶ、自然体験プログラムを、小中学校やNPO法人雨煙別学校と連携しながら磨き上げてまいります。
また、子どもたちとハサンベツ里山計画実行委員会が連携をしながら、ハサンベツ里山の保全や子どもたちの活動の場づくりに取り組んでまいります。
2.人と自然が共生するまちづくり
ふるさと自然体験教育の重要なフィールドである雨煙別小学校 コカ・コーラ環境ハウスやハサンベツ里山、ふるさといきものの里オオムラサキ館などを、町民の協力を得ながら継続的に整備し、維持保全活動を行うとともに、雨煙別川をサケの還るふるさとの川として整備し、いきもの豊かな川づくりを進めてまいります。
また、将来にわたって豊かな自然環境を守り次世代へと引き継ぐことができるよう、「人と自然が共生するまちづくり宣言」を実施 いたします。
第4分野 栗山町立北海道介護福祉学校
急激な時代の変遷が進む中で、本町では早くから超高齢社会の到来を見据え、北海道介護福祉学校を開校し、福祉のまちづくりを推進してまいりました。
しかしながら、近年の社会情勢の変化や介護福祉士を目指す高校生の減少などが、学校経営に大きな影響を与えている状況にあります。
この状況を打開し、本町をはじめ全道、全国に向けて優秀な介護人材を輩出していくことが、北海道介護福祉学校の果たすべき使命であることから、抜本的な経営改善に向けた取組が重要であります。
そのため、特に重視することを3点申し上げます。
1.学校経営改善計画の着実な推進
道内の介護福祉士養成校を取り巻く状況を踏まえ、「北海道介護福祉学校経営改善計画」に基づき、1学年1学級化に向けた取組を進めるとともに、学生確保対策を積極的に推進してまいります。
また、外部有識者を交えた「(仮称)学校評価委員会」において学校評価を実施するとともに、将来ビジョンや経営の在り方を確立してまいります。
2.地域包括ケアの一端を担う学校づくりの推進
令和3年度からの介護福祉士養成校におけるカリキュラム変更に向け、外部有識者を交えた教育課程編成委員会において、町内福祉施設での実習や地域活動など、事業者や町民との関わりをより重視したカリキュラム編成を行ってまいります。
また、教員の専門性を活用した福祉施設従業員のスキルアップや家庭介護者への講習会の開催など、地域包括ケアの一端を担う学校づくりを進めてまいります。
3.地域が一体となった介護人材の確保・養成に向けた取組の推進
本校の実績と経験に基づく知的財産を最大限活用し、本年度設置を予定している「(仮称)栗山町介護人材確保連絡協議会」を通じて、地域の介護人材の確保・養成の取組を進めるとともに、空知・全道へ支援の働きかけを行ってまいります。
結びに、令和2年度に向けた教育長並びに教育委員4名の決意の一端を申し述べます。
私たちは、これまでの「行動する教育委員会」の姿勢を堅持しつつ、子どもたちをはじめ、町民一人ひとりが生涯にわたって主体的に学び続け、ふるさとへの愛着や誇りを持ちながら未来の創り手となる人材の育成を目指し、町民とともにその創意に基づく栗山の教育を推進いたします。
町民の皆さん、議員の皆さん、並びに関係機関・団体の皆さんのご指導とご協力を心からお願い申し上げ、令和2年度の教育行政執行方針といたします。