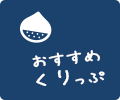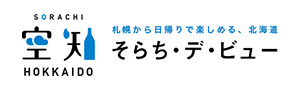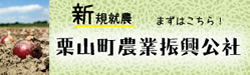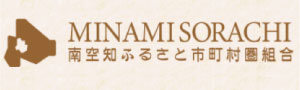本文
特定技能制度
特定技能制度とは・・・
中小・小規模事業者をはじめとした人手不は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みのことを言います。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html〈出入国在留管理庁HP〉
特定技能総合サイトについて
出入国在留管理庁では、特定技能制度の活用を促進するための取組として、制度説明会の開催及びこの制度に係る外国人向けの情報を多言語で発信する
特定技能総合支援サイト(https://www.ssw.go.jp/)の運営をしております。こちらで詳しく制度について学ぶことができます。
特定技能所属機関の協力確認書について
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能機関は市町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、この申請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。本改正の詳細については下記の出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
- 広報資料(PDF)<外部リンク>
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携<外部リンク>
- 特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A<外部リンク>
提出が必要な場合
◎初めて特定技能外国人を受け入れる場合
この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
◎既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
- 受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、この市区町村に対して一通提出します)。
- 該当する市区町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動するほかの特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- ただし、この別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して提出する必要があります。
- 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に提出する必要があります。
提出方法
下記の協力確認書(WordファイルまたはPDFファイル)をダウンロードして必要事項を記入のうえ、下記いずれかの方法でご提出ください。
※令和7年7月より協力確認書1枚で、派遣形態の場合でも「派遣先事業所の所在地」及び「特定技能外国人が雇用契約を結ぶ特定技能所属機関の所在地」を同時に確認可能な様式に変更となりました。
提出先:栗山町企画財政課企画グループ 宛
- 郵送または直接提出する場合
〒069-1512 北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番地(栗山町役場旧庁舎2階) - 電子メールで提出する場合
kikaku-g★town.kuriyama.hokkaido.jp ※★を@に直してお使いください - ファックス(FAX)で提出する場合
0123-72-3179