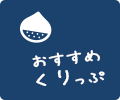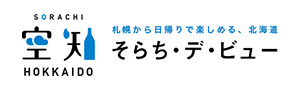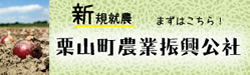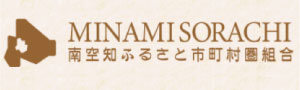本文
ひとり親家庭等医療費助成制度
栗山町では、母子家庭・父子家庭等のひとり親家庭等の方が病院等で診療を受けたときの保険診療に係る自己負担額について一部を助成しています。
なお、18歳到達年度末までのお子さんについては、栗山町の単独事業として北海道の基準に上乗せ(拡大)し「全額」助成しています。
※助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要となります。
※他の公費負担医療制度が利用可能な場合は、その公費負担医療制度が優先適用となります。
助成の対象者
- ひとり親家庭の20歳未満の「子」とその「親」
- 両親のいない家庭の20歳未満の「子」
※18歳到達年度末の翌日(4/1)から20歳到達月末までは、親または親以外に扶養(監護)されている場合のみ対象
ただし、ひとり親家庭等の主たる生計維持者(※)の方の前年(1月〜7月までは前々年)の所得額が、下表の限度額以上の場合、ひとり親家庭等医療費助成の対象となりませんが、18歳到達年度末までのお子さんについては 子ども医療費助成制度の対象となります。
(児童扶養手当の所得制限に準拠)
|
扶養親族等の数 |
限 度 額 |
(1)左の表中の扶養親族等の数が5人を超えるときは、その超える者1人につき38万円を加算した額とします。 |
|
0人 |
2,360,000円 |
|
|
1人 |
2,740,000円 |
|
|
2人 |
3,120,000円 |
|
|
3人 |
3,500,000円 |
|
|
4人 |
3,880,000円 |
|
|
5人 |
4,260,000円 |
※主たる生計維持者とは?
ひとり親家庭等の世帯の生計にかかる費用の大半を負担している方になります。
助成の範囲
|
親 |
入院・訪問看護の自己負担分 |
|
子 |
入院・訪問看護・通院(医科・歯科・調剤・柔道整復)の自己負担分 |
ただし、一部負担金(自己負担)、訪問看護に係る基本利用料を除く。
<助成の対象とならないもの>
- 標準負担額(入院時の食事代・居住費)
- 保険適用外医療費(検診・予防接種・オムツ・容器代・診断書料等)
- 要保護、準要保護を受給していて、これらで定める疾病で受診する場合
- 学校(休み時間、授業中、部活動など)でケガをして受診する場合
一部負担金(自己負担)
|
0~18歳に達する年度末まで |
全額助成(自己負担額は発生しません。) |
|
上記以降 |
住民税非課税世帯(※2)の方の場合、初診時に限り初診時一部負担金(※1)をお支払いください。 |
|
上記以外の方は、医療費のうち、1割相当額(※3)をお支払いください。 |
※1 初診時一部負担金とは? 医科 580円 歯科 510円 柔整 270円
※2 住民税非課税世帯とは? 世帯全員の方(別世帯の主たる生計維持者を含む)が、住民税非課税の場合をいいます。
※3 1割相当額をお支払いの方で、1ヶ月間の負担額が次の月額限度額を超えた場合、申請により払い戻しを受けることができます。 (月の初日から末日までの1割相当額の合計)
|
一部負担金 |
通院の限度額 |
入院(通院も含む)の限度額 (世帯単位) |
|
1割相当額 |
18,000円 (年額上限14万4千円まで) |
57,600円 (過去12か月に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円) |
受給者証が使用できる地域
・道内の保険医療機関等で使用することができます。(「健康保険証」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を一緒に保険医療機関等の窓口に提示してください。)
・道外で診療を受け、保険診療の自己負担額を支払った場合は、申請により一部負担金を差し引いた額の払い戻しを受けることができます。
ひとり親家庭等医療費の払い戻しの申請に必要なもの
|
(1) |
健康保険証 |
|
(2) |
受給者証 |
|
(3) |
領収書 |
|
(4) |
印鑑(スタンプ印以外) |
|
(5) |
保護者名義の預金口座が分かるもの |
|
(6) |
健康保険から高額療養費等の給付があった場合は、その支給額決定通知書 |
| (7) |
補装具にかかる費用の場合は、医師の証明書または作成指示書の写し(国民健康保険の被保険者以外の方は加入している健康保険の支給決定通知も必要となります。) |
医療費に対する高額療養費・付加給付金がある場合
・加入している健康保険により医療費に対する高額療養費・付加給付金の支給があるときは、その支給分は助成の対象となりません。
・加入保険により受領の委任をお願いする場合や、支給額を返還していただくことがあります。
交付申請の手続きに必要なもの
|
健康保険証 |
対象者全員の保険証が必要となります。 |
|
印鑑 |
親・世帯主・生計を維持している方の印鑑。 |
|
所得・課税証明書 |
対象者の属する世帯の方(主たる生計維持者を含む。)で転入者の方が必要となります。(所得額、控除額、扶養親族等及び住民税等の課税額の記載があるもの) ※源泉徴収票では受け付けできません。 |
次の場合は届出が必要です
- 主たる生計維持者が変わったとき
- お勤め先の変更等で健康保険が変わったり、健康保険証の記号・番号が変わったとき
- 住所、氏名が変わったとき(住民票の届出を行なった後)
- 受給者証を紛失等により再交付を受けるとき
※婚姻等(事実婚)により受給資格がなくなったときは、速やかに受給者証をお返し願います。
※婚姻等(事実婚)により受給資格を喪失した場合、その事実が発生した日まで遡り、医療費の返還を求める場合があります。
<事実婚とは>
夫婦としての共同生活と認められる事実が存在する状態。同居している場合のほか、頻繁に定期的な訪問・生活費援助・税法上の扶養親族になる等がある場合、同居していなくても事実婚成立となります。
※「届出に必要な物」 健康保険証・受給者証・印鑑