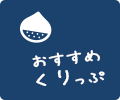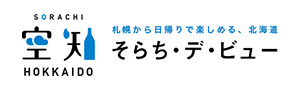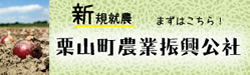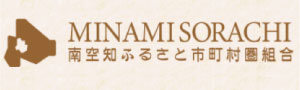本文
国民健康保険制度の変更(H30.4~)
国民健康保険は、全ての国民が安心して医療を受けることができる基礎となる健康保険の一つであり、各市町村が運営しています。加入者の皆さんが納める保険税と国等からの補助金により成り立っていますが、国保の加入者は「退職者が多く年齢構成が高く、医療費水準が高い」「低所得者が多い」という構造となっているため、今後、少子高齢化の進展により、加入者の減少に伴い各市町村単位では安定した運営が困難になるなどの課題があります。
そのため、国民皆保険制度を維持するため、平成30年4月から北海道と市町村がともに国保の運営を担い、北海道が財政運営の責任主体となります。
制度改正後の都道府県と市町村の役割分担
| 改革の方向性 | ||
|
1.運営のあり方 (総論) |
・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の中心的な役割を担い、制度を安定化 ・都道府県が、都道府県内の統一的な運営の方向付としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
|
| 都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
| 2.財政運営 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
| 3.資格管理 |
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.5も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (被保険者証等の発行) |
|
4.保険税の 賦課・徴収 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定・公表 |
・標準保険料(税)率等を参考に保険税率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
| 5.保険給付 |
・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
| 6.保健事業 |
市町村に対し、必要な助言・支援 |
・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
制度改正に伴う国保加入者(被保険者)の主な変更点(予定)
変わらないこと(これまでどおり町が窓口)
| ・国民健康保険の加入・喪失手続き | ・保険者証などの交付 |
| ・療養費の手続き | ・高額療養費の手続き |
| ・出産一時金の手続き | ・葬祭費の手続き |
| ・保険税の賦課・徴収 | ・特定健診等の保健事業 |
変わること
| 説 明 | |
|
国保加入者の 資格管理 (都道府県単位化) |
都道府県も国保の保険者となるため、これまで市町村ごとに行っていた被保険者の資格管理を都道府県単位で行うこととなります。 そのため、被保険者が北海道内の他市町村へ住所異動した場合でも、資格の取得や喪失が生じないことになります。 ・北海道内の他市町村へ住所異動があった場合、元の市町村発行された被保険者証は使用できなくなります。異動先の市町村で被保険者証を発行してもらう手続きは今までと同様に行う必要があります。(道外への住所異動の場合には、資格の取得や喪失手続きが生じます。) ・同一都道府県内の住所異動の場合は、市町村単位で「適用開始・終了年月日」として管理されます。 (今までは、各市町村で「資格取得・喪失年月日」として管理) |
| 被保険者証等の様式 |
都道府県も国保の保険者となることに伴い、「適用開始・終了年月日」の創設等により、被保険者証などの様式が変更となります。 ※北海道では、新たな様式への切り替え時期を平成30年8月1日からとすることで検討されています。 |
|
高額療養費の多数回該当通算方法 |
これまでは、市町村をまたいで異動した場合、高額療養費の多数回該当は通算されませんでしたが、同一都道府県内での異動の場合で、世帯の継続性が保たれている場合、多数回該当数が通算されるようになります。 ※多数回該当とは~医療費が高額となった場合、所得に応じて自己負担額が一定額までで済む制度で、1年間のうち高額療養費に4回以上該当した場合(多数回該当)、自己負担額限度額が変わります。 |