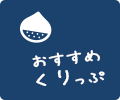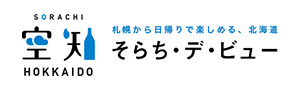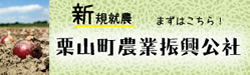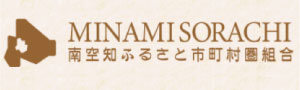本文
ケアラー支援講演会|ヤングケアラーの支援を考える
令和5年9月28日(木)に、くりやまカルチャープラザ「Eki」においてケアラー支援講演会を開催しました。

テーマは「見守り・支援ってなんだろう?~ヤングケアラーの子どもたち~」
今社会が関心を寄せているヤングケアラーの支援について110名の参加者が熱心に講演を聴かれていました。
参加者からは、ヤングケアラーは身近にいないと思っていたが、実例には身近に数名いるのだと感じ、誰にも相談できない方、かかえこんでいるという現状を知ることができましたや、パネルディスカッション、素晴らしかったです。色々と気付かされました。このことに思いを寄せたいと思いました、子どもの心の声に気づける大人になりたいと思いましたなどの感想を頂きました。
基調講演
基調講演は、令和4年度家庭教育講演会でも講演して頂いた島根大学法文学部法経学科教授の宮本恭子氏。昨年の家庭教育講演会では、ヤングケアラーに対しての理解とその接し方を中心に講演していただきましたが、今回は、ヤングケアラーを支援するにあたっての地域づくりを含めて、具体的にどのように支援体制を構築するかを中心に講演されました。
講演内容は、令和4年11月に町と教育委員会で実施したヤングケアラーの実態調査について、宮本教授が行った分析結果を報告されました。その報告には、栗山町にはヤングケアラー及びヤングケアラー予備軍が1学級に5~6人いることがわかり、その傾向としては、全国に比べて自分に自信が持てないヤングケアラーが多いことが特徴であること。ヤングケアラー予備軍であっても、介護や福祉に肯定的なイメージを持っている傾向があり、子どもたちのケアに対する肯定的な捉え方は、ケアラー支援条例の制定と取組みが町民全体に浸透している結果であり、ヤングケアラー支援をケアラー支援から切り離さず、ケアラー支援の中のヤングケアラー支援を行っていくことが重要だと話されました。
また、ヤングケアラーを支える地域づくりと支援体制を構築する上では、子どもたちからの相談事例は多くないため、関係者がどれだけ、ヤングケアラーに「気づく」かとが大切であること。そして、見守り・支援ができる地域づくりには、様々な支援主体ができることを模索し、連携・協働し合う土壌を作ること(地域の基盤づくり)や多職種・多機関連携にあたり、支援主体内での統括責任者の所在と、互いの役割の明確化すること、顔の見える関係づくりを行う事、緩やかな見守り・支援を継続するには、ヤングケアラーとその家族と地域が接点を作ることが必要であると指摘されました。
そして、これからのヤングケアラー支援を見据えた場合、大切なことを6点挙げられました。
(1)本人と家族の意思を尊重しながら、本人にとっての選択肢を増やすこと。
(2)一人で抱え込まなくても良い社会資源(相談場所・SNSなどのオンラインを含む)を提示し、なければ一緒に創っていくこと。
(3)「子どもとつながり、地域で見守る仕組みづくり」
(4)助けを求める、助けを受けることができる「受容力」を高めるような働きかけを多分野が連携して実施する。
(5)ケアを無くすのが難しい場合は、「withケア」の視点を持ちながら支援すること。
(6)ヤングケアラーの援助希求力・レジリエンス(回復力・適応力)の向上を支援すること。

島根大学 宮本恭子教授
パネルディスカッション
パネルディスカッションは「気づく・つなぐ・地域で支える~それぞれの立場から~」というテーマで行われました。
パネリストは、栗山町社会福祉協議会業務係長の冬野大希氏、栗山町住民保健課松田茂弓氏、そして、栗山とゆかりのある北海道介護福祉学校卒業で、現在、放課後等デイサービスや子ども食堂を経営されている特定非営利活動法人あい理事長の吉川淳也氏が実践発表を含めて発言され、ファシリテーターは空知管内ヤングケアラーコーディネーターの浅沼寿実氏(光が丘学園子ども家庭支援センター主任相談員)が務めました。
冬野氏は、これまでの社会福祉協議会によるケアラー支援活動から、条例制定までの流れと、現在、いのちのバトン(救急救命キッド)配布世帯に対して行っている傾聴ボランティア(ケアラーサポーター)の訪問活動に関して発表し、積極的に働きかける「顔の見える地域の関係づくり」を行っていくことを発言されました。
松田氏は、栗山町における保健師の活動を紹介。乳幼児期から高齢者までの幅広い保健師の活動から、健康に関して予防的な視点から、家庭訪問により家庭に入っていく事が可能であり、家の中だからこそできる相談や心の内側を受け止めながら、支援の中でヤングケアラーも含めた、その人が必要としている社会資源を見つけてつないでいく役割があることを、事例にも触れながら発言されました。
吉川氏は、自身が経営されている放課後等デイサービスや子ども食堂についてを説明、ヤングケアラーが数多くいることと具体的な事例を上げながら説明する一方で、緊急事態があったとしても札幌市では、児童相談所による一時保護などの収容力が低く、民間サービスがその受け手となり、子どもたちを支えている現状を話されました。特に、現場で子どもたちを見ている中での、ヤングケアラーになる要因としては、家族全ての健康状態・障がいの程度・発達の遅れがあるケースや、保護者が子どもらしい子ども時代を経験してこなかった成育歴であったり、家庭内連鎖~きょうだい間連鎖(年上の兄弟を見て、年下は真似をする)、情報の不足、や社会の資源不足を挙げ、同じ「まち」に住む一員として、近所付き合いの大切さや、きめ細やかなネットワークの構築、ヤングケアラーに関心を持つことを訴えられました。
全体討議では、吉川氏より、子どもの声を粗末にしたくない、「困った感」のない、困ったことがわからない子たちは、その言語化ができないこと。学校では、十分に教員と話ができない子どもたちがいるからこそ、学校と現場・子どもたちとの距離を縮めたいこと、小さな命が消えていかないために、官民一体となって「いのち」向き合いたい、考えたいと訴えられました

パネリスト(左から、松田氏、冬野氏、吉川氏) 吉川淳也氏