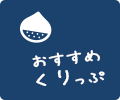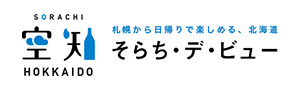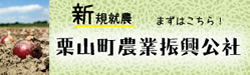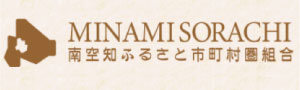本文
令和7年度 ケアラー支援講演会
「お父さん、なぜ線路に入ったのですか?~認知症介護で苦悩する母の思いと家族の心境~」
9月30日(火)にくりやまカルチャープラザ「Eki」において、ケアラー支援講演会が開催されました。
講師は認知症鉄道事故裁判のご遺族である高井隆一さんに講演していただきました。
テーマは「お父さん、なぜ線路に入ったのですか?~認知症介護で苦悩する母の思いと家族の心境~」
講演には町内外合わせて、約150名が講演会に参加されました。
高井 隆一 さん
会場内の様子
高井隆一さんのお父様は2000年12月に認知症発症し症状が進む中、家族総動員で介護にあたってきたそうです。強い外出願望がある中で、服に名札を縫い付けたり、人感センサーを用意して出かける前に対応することもあったと話されました。外出しても無事に帰って欲しいとの家族の思いの一念だったそうです。
そんな中、発症してから7年後、鉄道事故。家族が一瞬目を離した隙に一人で外出、隣駅構内の線路上にての事故死。トイレを探している中で駅構内におりたのではないか。そう話されていました。
その半年後にJR東海から720万円の請求。そして裁判になった。
・JR東海は、「専門医を受診すべきだった。特養に入所すべきだった。衣服に縫い付けた名札は「ただの甘えという他ない」。」などと全額支払いを主張
・私たちは、「国の方針に沿って在宅介護していただけ。家族総動員で介護していた。一瞬も目を離さないのは困難。JR側にも施設管理責任がある」と主張
2013年の第一審名古屋地裁判決では、同居していた妻と、介護方針を決定していた長男に監督責任があった(民法714条)。720万円全額を支払うこと。
介護に関与していなかった長女・次女・次男には支払い義務はないという判決であり、全面敗訴、かつ介護に関与すればするほど責任を問われる内容だった。
在宅介護をする家族にとっては絶対にあってはならない判決であり。直ちに控訴したそうです。
2014年第二審名古屋高裁判決「妻は2分の1の、360万円を支払う判決になったが、JR東海は納得せず、直ちに上告。あくまで全額支払いを求めた。
当時の法曹界の見解では、「当然の判決だ」、「不法行為によって損害が出ているのだから被害者救済が正義だ。本人に責任能力がないなら家族が弁済するのは当然だ。」、「控訴審判決は、介護の大変さにも配慮した、知恵を絞ったよい判決だ」と判決を肯定的に受け止める見解が多かったと話されました。
そんな中で、逆転勝訴に至るにはメディアの報道の力も助けになったといいます。
「これでは在宅介護はやれない。裁判所は認知症の人を閉じ込めておけというのか」という意見や、認知症の人と家族の会からは 「家族に責任を押し付けた一審判決は取り消すべき」という意見がでて力強かった。
そして、2016年に最高裁の判決を迎えました。
「私たち家族には責任がない」、「介護などの事情を総合考慮して責任を判断すべき。家族に責任はない。」という判決が下されました。
認知症になっても、地域で在宅で安心して介護できる礎となる判決だと高井さんは受け止めています。
最高裁判決までの道のりで、認知症への理解が深まり、全国で様々な施策が一気に活発化したこと。愛知県大府市は2017年に全国初の「認知症に対する不安のないまちづくり推進条例」制定されたことや「個人賠償責任保険」の登場による被害者救済策が生まれたこと。「徘徊」という言葉から「ひとり歩き」などへの言葉の使い替えなど様々な動きにつながった。
認知症の人が安心して生活できるまちづくり、そして-地域でできることを考えると、「認知症」という言葉へのの偏見を払しょくすること。「認知症であるということを知ってもらうこと」、認知症サポーターなど理解者・支援者を増やしていくこと。さりげない・でも勇気を持った「今日は良い天気ですね。どちらにお出かけですか?」が、その人の人生を救うことになるかもしれない。今なら、父親が助かったかもしれないとそう思い返されていました。
認知症ヘルプマークと見守り・安心キーホルダー
高井隆一さんは、お父様の鉄道事故死をきっかけとして、認知症になっても安心して暮らせる社会を目指して講演などの活動をされています。その中の1つが認知症当事者のヘルプマークがあっても良いのではないかという思いから、愛知県大府市と相談し、認知症ヘルプマークが生まれました。
本講演会では、そのことに高井さんに触れていただきながら、認知症ヘルプマークを活用した見守り・安心キーホルダーを作成することを発表しました。

キーホルダー(表) キーホルダー(裏)
講演会の感想
来場された方からの感想を紹介します。(抜粋)
・ご本人が世に今後残してはいけない、判例にしてはならないとそのとき当たり前というものをそのまま当たり前としないで立ち上がり困難に打ち勝ったという事実が印象に感じた。
・認知症という誰しもありうる病気に対しての認知や知識を深めるきっかけが痛ましい事故事故だった事。悲しむ間もなく裁判になってしまい、ご家族の失望感が大きかっただろうと思います。最後まで戦った結果、世間的にも認知症への理解が深まるきっかけになっている事は大きな進歩だと思います。
・老いてくると誰もが認知症になると考えられるので、特別な事ではないと認識されることが広まってほしい。講演を聞いて家族はとても大変な苦労があると再認識されました。この話をたくさんの人に聞いてほしいと思いました。
・徘徊ではなく、理由が本人なり・自分なりに目的があった(あって)歩いていたと妻が言ったとの言葉に胸が詰まりました。
・「徘徊」という言葉について深く考えるきっかけとなりました。世の中は少しずつではあるが変わってきていると実感しました。もっと日本の考え方や高齢者、認知症の方に対する見方と理解が広まれば良いなと思っています。
・本日は、認知症に対する講演会を開いていただきありがとうございました。今でも認知症に対する誤った解釈を持つ方が多いでしょうが認知症に対する正しい知識と対応が全国に広がるよう応援しています。
・現在介護福祉士の養成校に通っています。授業では基本的なことを学べますが家族の声を聴くことはなかなか機会がないので今回この貴重な講話を聴講できて良かったです。ありがとうございました。
・ケアラーの日々の生活、認知症になってしまった本人の不安な気持ちに少しでも寄り添える自分でありたいと強く思いました。貴重なお話有難うございました。