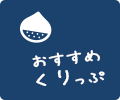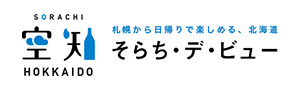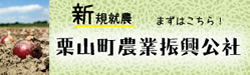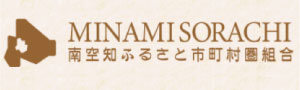本文
補装具費の支給
身体の障がいを補うための用具の購入や修理、レンタル費用の一部を支給します。
補装具とは
(1) 身体機能を補完または代替えし、かつその身体への適合を図るように製作されたもの
(2) 身体に装着することにより、その日常生活においてまたは就労もしく就学のために、長期間に渡り継続して使用されるもの
(3) 医師等による専門的な知識に基づく意見または診断に基づき使用されることが必要とされるもの
以上、3つの要件すべてを満たすものと定義されています。
ただし、予備のための補装具や日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。
障がい種類別の補装具費支給対象種目一覧
| 障がいの種類 | 種目 |
|---|---|
| 肢体不自由 |
義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ ※18歳未満の障がい児のみ 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
| 重度の肢体不自由かつ音声・言語障がい | 重度障害者用意思伝達装置 |
| 視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障がい | 補聴器 |
| 難病患者等 | 車椅子、電動車椅子、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、装具、歩行補助つえ及び身体状況に応じて個々に必要と判断される補装具 |
補装具費の支給を受けるには
補装具の支給を受けるには、補装具の種目に対応した身体障害者手帳の所持者または難病患者等であって、判定により補装具が必要であると認められる必要があります。
補装具費支給までの流れ
(1)役場福祉課(5番窓口)へ申請
(2)判定機関(北海道立心身障害者総合相談所)により、支給の要否判定を行います。
※申請される補装具によって、本人の来所等による直接判定や、判定機関の判定を要せず補装具費支給意見書により支給決定する補装具もあります。
| 判定が必要な補装具 |
直接判定 |
義肢(骨格構造義肢)、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、特例補装具 |
|---|---|---|
|
文書判定 |
義肢(殻構造義肢・骨格構造義肢のソケット修理)、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子(オーダーメイド)、重度障害者用意思伝達装置(簡易なもの) | |
| 判定不要な補装具 | 義眼、眼鏡、車椅子(レディメイド)、歩行器、盲人安全つえ、歩行補助つえ | |
※特例補装具とは、補装具の種目に該当するもので、基準に規定されている補装具の範囲内では対応できない場合に製作、購入される補装具になります。
(3) 役場より補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券の発行(郵送にて送付)
※申請後、判定に日数を要すため、支給決定まで1か月~2か月程かかる可能性があります。
(4) 利用者が、補装具費支給券を業者に提示し、用具の支給を受ける
(自己負担額がある場合は、業者にお支払いいただきます)
申請に必要なもの
・医師意見書(補装具費支給意見書)
・補装具製作事業所が作成した御見積書
・身体障害者手帳、難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証等 ※難病患者等に該当する方)
・印鑑
再支給・修理について
一般的には、前回判定を受けて支給されたものと同一の型式である等、特に医学的判定を要しないと認められる場合は、再度の判定を行わず支給決定できます。
しかし、骨格構造義肢、特例補装具については、前回支給されたものと同一の型式であっても、その都度身体状況の確認が必要なことから直接判定となります。また、使い分けの必要がある場合等2個目の補装具を希望される場合は、個数の例外であることから判定が必要となります。
※児童で支給された補装具について、18歳を超えてから再支給及び修理する場合や、自費で購入するなど制度を利用しないで使用している補装具の修理をする場合等は、新規支給に準じ判定を行います。
耐用年数について
通常の装用状態において修理不能となる予想年数です。原則的には、耐用年数を超えてから再支給が可能となります。
障がいの状況や使用頻度等により修理不能となるまでの期間に長短が生じるため、通常の装用状態において修理不能となった場合や災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合は、耐用年数以内であっても再支給の対象となる可能性があります。
利用者負担上限額
| 区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯または市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※利用者が18歳以上の場合は、「本人と配偶者」のみを世帯とし、負担上限月額を決定いたします。
※基準額を超える金額の補装具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの区分でも全額自己負担となります。
子どもの補聴器購入費等助成
聴覚障がいに係る身体障害者手帳の交付対象とならない、軽度・中等度の難聴がある満18歳未満のお子さまの補聴器の購入または修理にかかる費用を助成します。詳しくは、以下リンクの「子どもの補聴器購入費等助成」のページをご覧ください。
補装具費代理受領の取扱いを希望される事業所の皆さんへ
補装具費代理受領の取扱いを希望される事業所の方は、事前に登録申請が必要となります。
申請方法については、以下リンクの「補装具費代理受領登録の申請について」よりご確認ください。