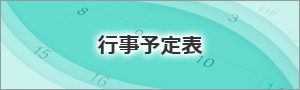本文
議会用語集(た行)
用語集一覧
議会で使われる用語の中には、一般生活であまり耳にしないものが多くあります。わかりにくい議会用語を五十音順に解説します。
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 |
| は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
た行
陳情(ちんじょう)
議会に対し、町の仕事に関することや地域の身近な問題について、文書で意見や希望を述べることをいいます。なお、形式としては請願と同じですが、陳情の提出には紹介議員は必要ありせん。
通告書(つうちしょ)
議員が議会の会議で発言したいときに、あらかじめ議長に発言の主旨などを告げ知らせることをいいます。その様式を通告書といい、栗山町議会では、定例会の一般質問の通告書を傍聴される方にもお配りしています。
定足数(ていそくすう)
会議を開くために最低限必要な出席議員数のことをいい、地方自治法第113条により議員定数の半数以上となっています。栗山町議会の場合、議員定数は12人ですので、議長を含む6人以上の議員が出席しなければ本会議を開くことができません。
定例会(ていれいかい)
定期的に招集される議会のことをいい、栗山町議会では、3月、6月、9月、12月に定例会を開きます。なお、町長は議会で審議する事項がない場合でも、定例会は招集しなければなりません。
答弁(とうべん)
本会議や委員会などで、議員(委員)の質問・質疑に対して町長をはじめ執行機関などが答えることをいいます。
討論(とうろん)
議題となっている事項が採決される前に、議員が賛成または反対の立場にたって意見を表明することを討論といいます。討論の目的は、単に自分の賛否の意見を明らかにするだけでなく、まだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自分の意見に賛同させることにあります。
特別委員会(とくべついいんかい)
特定の事項について詳しく調査するため、必要に応じて設置する委員会のことをいいます。特別委員会が設置されるのは、次のような場合です。
- 政治的に必要があることがらを審議しようとするとき
- 2つ以上の常任委員会にまたがることがらを審議しようとするとき
- 連合審査会(常任委員会どうしが合同して審査をすること。)では目的が果たせないとき
- 総合的な施策を樹立しようとするとき
- 地方自治法第100条に基づく調査をしようとするとき(この目的のために設置される特別委員会は100条委員会と呼ばれています。)
- 議員としての資格や懲罰などを審査するとき
動議(どうぎ)
本会議や委員会などで会議の進行又は手続きに対し、議員から行われる提案で、議決を要するものです。